10月1日付で登録予定です。
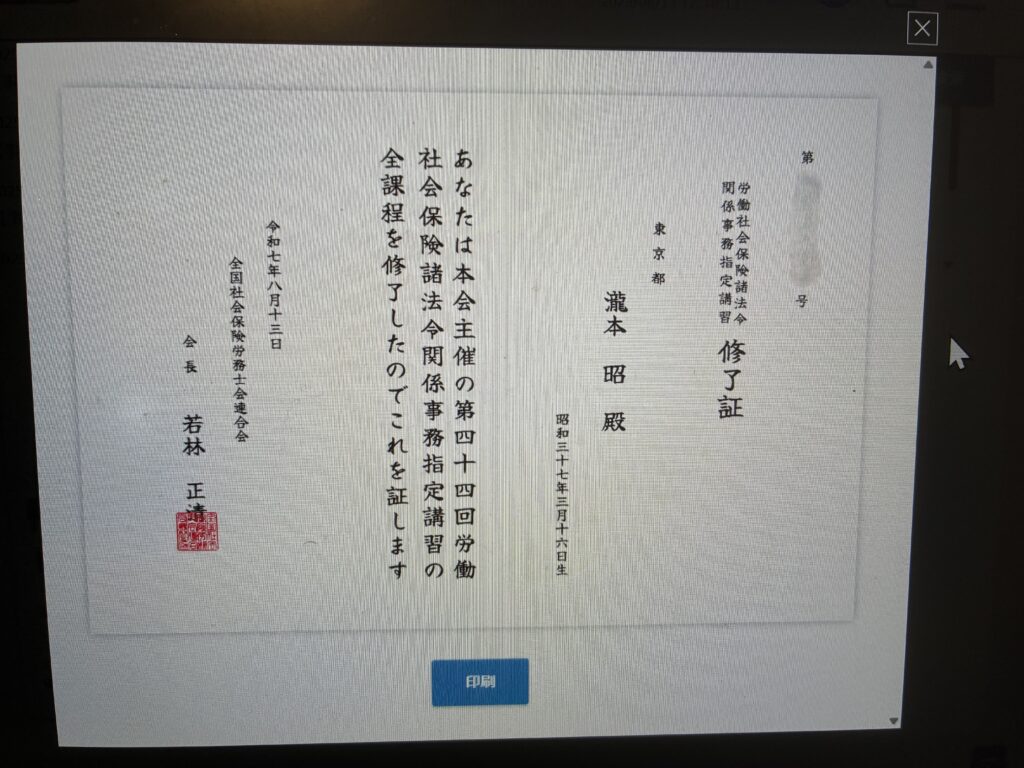

働き方を見直して家族と社会の未来を変えよう
10月1日付で登録予定です。
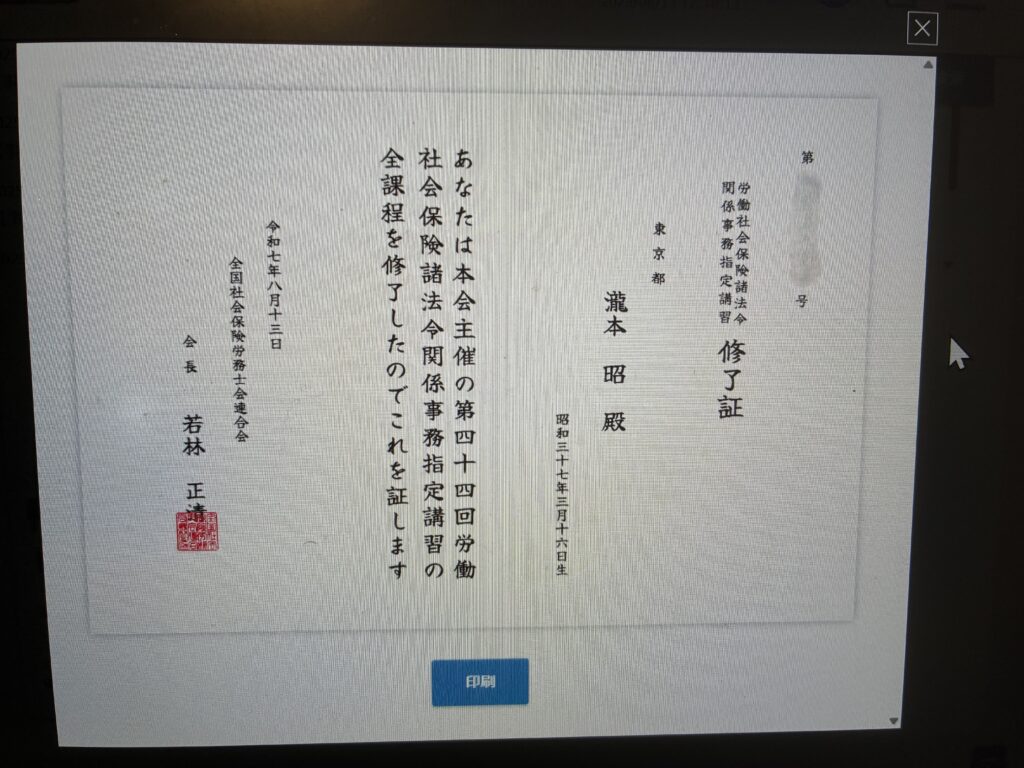
「働き方改革、うちでは人事部が中心で進めています」
「総務がテレワーク制度の管理をしています」
——このように、人事や総務が中心になって進めているケースは多いと思います。
もちろん、制度設計や規程整備など、初動において人事・総務が果たす役割は非常に重要です。
しかし、改革が“人事部の仕事”のままで止まってしまうと、現場には根づきません。
働き方改革を真に企業文化として定着させるには、「部門横断」で推進する体制づくりが不可欠です。
現場に合わない制度を押し付けてしまうと、形骸化や反発が起きやすくなります。
「また本社が勝手に始めた」という印象を持たれると、現場の協力は得られません。
ある部署だけが積極的、別の部署は様子見…という状態では、改革は社内に浸透しません。
👉 推進チームは、制度運用の実態把握、改善案の提案、社内の意識啓発などを担います。
👉 一律の制度を押しつけるのではなく、「それぞれの最適解」を一緒に探すことが重要です。
👉 これにより、「柔軟性と統一感」を両立させ、納得感ある運用が実現します。
現場やミドル層を巻き込むには、経営層が明確に旗を振ることが必要です。
というメッセージを、経営トップが発信するだけで、組織の空気は変わります。
10回にわたってお届けしてきた「働き方改革推進者向けブログシリーズ」。
今回は一区切りとなりますが、今後も引き続き、組織文化に根ざす働き方改革の実践知を共有していきたいと思います。
「せっかく働き方改革を進めたのに、人が定着しない」
「制度は整えたのに、職場の空気がギスギスしている」
「会議で本音が出てこない、若手が何も言わない」
こうした相談は、働き方改革を支援する中で本当によく聞きます。
どれだけ制度を充実させても、人が安心して声を上げられない職場では、本当の意味での改革は根づきません。
今、多くの企業で注目されているのが、「心理的安全性(Psychological Safety)」です。
心理的安全性とは、
「このチームでは、何を言っても否定されない」
「自分の意見を言っても、恥をかかされない」
という、チーム内の安心感のことです。
もともとはGoogleのプロジェクト研究で「成果を出すチームの共通点」として話題になりました。
ポイントは、「仲良し集団」ではなく、意見の対立や違いを安心して出し合える土壌があることです。
これでは、働き方改革で目指す自律性や創造性は生まれません。
意見を言いやすくするには、管理職や会議の進行役が、
「否定しない・さえぎらない・最後まで聞く」
という姿勢を徹底することが大前提です。
どんな小さな発言でも「ありがとう」と受け止めるだけで、発言する人のハードルはぐっと下がります。
「問題を報告したら怒られる」という空気があると、誰も報告しなくなります。
むしろ、ミスや課題を共有することを「当たり前」にすることで、再発防止や学びにつながります。
こうしたルールや文化が、安心感を生みます。
心理的安全性は、上下関係だけでなく同僚同士の関係性でも生まれます。
こうした“ちょっとしたつながり”が、普段の発言や行動を後押しします。
心理的安全性は制度ではなく、日々のコミュニケーションの積み重ねで育まれます。
こうした空気があるからこそ、
制度が活き、働き方の選択肢が使われ、挑戦する人が増えるのです。
次回は、「『なんとなく不満』を言える職場が強い — 離職防止の新常識」をテーマに、従業員がモヤモヤを溜め込まずに済む環境づくりについて掘り下げます。
働き方改革、テレワーク、フレックス、裁量労働制……
多様な制度が広がる中で、現場からはこんな声を耳にすることがあります。
「うちは働き方が自由すぎて、だらけてしまう人がいる」
「管理を緩めたらサボる社員が増えた」
「結局、優秀な人に負担が集中している」
働き方を柔軟にしたはずが、「甘い職場」になってしまっていないか。
この違いを見極め、「ゆるいけど成果が出る職場=自律型組織」をどうつくるかが、これからの大きな課題です。
ゆるい職場
→ 制約が少なく、時間や場所の自由度が高いが、成果に対する責任は自分で引き受ける
甘い職場
→ 制約がなく自由に見えるが、成果が出なくても注意されない/役割が曖昧/責任が問われない
つまり、「自由」と「責任」がセットになっているかどうかが大きな違いです。
では、どうすれば「自律的に動ける自由な職場」をつくれるのでしょうか?
ポイントは3つあります。
裁量を広げるなら、何を成果とするかをクリアにする必要があります。
目標が曖昧だと、責任を果たす範囲も不透明になります。
「自由に働いていい」が機能するのは、評価軸が明確だからこそです。
自由度が高いほど、「誰がどこで何をやっているか」が見えなくなるリスクがあります。
そこで、
など、アウトプットが可視化される仕組みが必要です。
「放任」と「信頼」は別物です。信頼は情報の透明性から生まれます。
自由に任せる以上、失敗は避けられません。
大事なのは、失敗したときに「責める」ではなく、「学びに変える」カルチャーを用意することです。
これにより、「自分で考えて動くこと」を恐れない風土が育ちます。
柔軟な働き方は、放置プレイとは違います。
自律型組織の裏には、管理職の新しい役割が存在します。
自由と責任を両立できる場を作るのは、現場リーダーの腕の見せ所です。
次回は、「人が辞めない職場に必要な『心理的安全性』とは?」をテーマに、働き方改革の土台を支える“安心して意見を言える職場づくり”のヒントをお届けします。
コロナ禍をきっかけに一気に普及したテレワーク。
しかし、2025年の今、「出社回帰」の動きが見られる企業も増えています。
こうした声は、どの企業でも共通です。
一方で、出社だけに戻してしまえば、従業員の柔軟性や働きやすさは逆戻りです。
そこで注目されているのが、「ハイブリッドワーク」という選択肢です。
しかし、この形を成功させるには、「ただ在宅と出社を混ぜればいい」という単純な話ではありません。
多くの企業がハイブリッドワークを取り入れているものの、
といった課題に直面しています。
つまり、出社前提の職場をベースにして“リモート勤務”を無理やり乗せているだけでは、ハイブリッドの強みを活かせないのです。
ハイブリッドワークを形だけにしないためには、「オフィスは何のために存在するのか」を問い直す必要があります。
たとえば:
こうして、出社する理由を明確化することで、出社も在宅も意味のある選択肢になります。
「何曜日は必ず出社」ではなく、
「この業務、このミーティング、この研修のために出社する」という目的とセットのルール化が有効です。
オフィスにいる人だけで物事が決まると、リモート勤務者のエンゲージメントは下がります。
こうした情報の公平性の確保が重要です。
雑談、ワークショップ、リアルイベントなど、対面でしか得られない価値を意図的に設計しましょう。
「わざわざ集まる意味がある」ことで、出社への納得感と満足度が上がります。
結局のところ、ハイブリッドワークを成功させるのは「仕組み」だけではなく、
といったマネジメントの進化です。
単なる制度ではなく、「文化としての柔軟性」を根づかせることが、働きやすさと成果を両立させます。
次回は、「『ゆるい職場』と『甘い職場』は違う — 自律型組織をつくる仕掛け」をテーマに、働きやすさと自律性のバランスをどう保つかを掘り下げます。
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「働き方改革」。
この2つの言葉は、今や企業経営に欠かせないキーワードになりました。
しかし、現場ではこんな声をよく耳にします。
「最新の勤怠管理システムを入れたのに、結局紙の帳票も残っている」
「チャットツールを導入したけど、誰も使いこなせていない」
「結局“便利になった”という実感がない」
多くの企業が陥るのは、「ツールを入れただけで改革したつもりになる」状態です。
本当の意味でのDXと働き方改革を両立させるには、ツール導入だけで終わらない“文化づくり”が不可欠です。
なぜシステム導入だけでは何も変わらないのでしょうか?
失敗する現場に共通するのは、「業務プロセスの棚卸しをしていない」ことです。
これでは結局、デジタルとアナログの“二重運用”が発生し、かえって現場の負担が増えてしまいます。
本来、DXも働き方改革も、目的は「時間や場所に縛られない柔軟で生産性の高い働き方を実現すること」です。
ツールはあくまで、その実現を支える手段に過ぎません。
導入がゴールになってしまうと、「使うこと自体が目的化」してしまい、現場に負担を強いるだけの存在になります。
ツールに合わせて業務を変えない限り、真の意味での効率化はできません。
現場のプロセスを可視化し、ムダを洗い出すことから始めましょう。
「現場でどこが困っているか」「どこで止まっているか」は、実際に使う従業員しかわかりません。
こうしたプロセスを通じて、システムを“使えるもの”に進化させます。
どんなに優れたツールも、使われなければ意味がありません。
「使っても大丈夫」「これで仕事が回る」という安心感を育てることが、文化定着の鍵です。
DXは、単なるIT化とは違い、企業文化や働き方を変える変革そのものです。
「新しい仕組みをどう根付かせるか」
「誰が旗を振るか」
「小さな成功体験をどう積み上げるか」
この人と文化への投資こそが、働き方改革とDXの真の成果を生みます。
次回は、「ハイブリッドワーク成功の鍵 — 『職場の再定義』をしてみませんか?」をテーマに、リモートと出社を組み合わせた柔軟な働き方のベストプラクティスを考えます。
制度をつくった。
ルールを整備した。
説明会も開いた。
——それでも、現場が動かない。
働き方改革の推進において、最も多く寄せられる悩みがこれです。
「制度は整ったのに、なぜ現場は変わらないのか?」
その答えは一つ。「腹落ちしていない」からです。
つまり、従業員一人ひとりが、自分ごととして納得していないのです。
今回は、現場の納得感を高め、実行へとつなげるための「伝え方」「巻き込み方」「対話のあり方」に焦点を当てます。
「生産性向上」や「競争力強化」という言葉は、現場にとっては遠い話です。
「それが自分の働き方にどう関係するのか」が見えなければ、動きません。
「制度の使い方」だけ説明され、「なぜやるのか」「何を変えたいのか」といった背景や目的が語られないと、受け手の理解は浅くなります。
従業員にとって「また何か始まった」「決められたからやらされている」という印象になってしまうと、表面的な行動しか取られません。
現場に変化を起こすには、「伝える」だけでなく「納得してもらう」ことが必要です。以下の3つが特に重要な観点です。
制度の概要ではなく、「なぜ今、改革が必要なのか」「どんな問題を解決したいのか」から始めることで、従業員の共感と関心を引き出せます。
✕「来月から在宅勤務制度を導入します」
◎「通勤時間や家庭事情で困っている声が多く、柔軟な働き方が求められています。そのために——」
制度導入の狙いが組織目線だけで語られると、従業員は「自分には関係ない」と感じがちです。個人の立場でどんな良いことがあるのかを示しましょう。
例:
一度の説明会で終わらせず、小規模な座談会、意見交換、1on1などの場を通じて、疑問や不安を受け止めることが大切です。
「話せる場がある」という安心感が、現場の理解と協力を促進します。
制度を“現場仕様”にするには、実際に使う人の声を反映させることが不可欠です。
そのためにも、次のような継続的な対話の場づくりをおすすめします。
アンケートや面談での意見を拾い、可能な限り制度や運用に反映し、変更点は「●●さんの声で変わりました」と伝える。
この繰り返しが、現場の信頼を築きます。
改革に理解ある現場リーダーやミドル層を早期に巻き込み、現場発の推進役にすることで、現実的な落とし込みが可能になります。
次回は、「DXと働き方改革—システム導入だけでは何も変わらない」と題し、デジタルツール導入が目的化してしまう失敗例と、真の“業務改革”につながるアプローチを解説します。
働き方改革というと、
「残業時間の削減」
「所定労働時間の短縮」
「効率化による時短」
といった“時間”の削減に注目が集まりがちです。
もちろん、長時間労働の是正は改革の大きな柱です。しかし、「時短」だけが目的になってしまっていないか、今こそ立ち止まって考えてみる必要があります。
時間を減らすことにばかり意識が向くと、「早く帰ること」が目的化し、かえって納得感のない成果主義や働きづらさを招くリスクがあるのです。
短時間で成果を出すことが求められるあまり、じっくり考える仕事が敬遠され、「手早くできること」が評価されがちに。
例えば子育てや介護との両立で時短勤務の人と、長く働ける人の間に「評価の不公平感」が生まれやすくなります。
職場の意識が追いつかないまま「早く帰れ」が徹底されると、むしろ働き手のストレスや孤立を招くこともあります。
働き方改革の目的は、単に労働時間を短くすることではなく、限られた時間の中でいかに成果を出し、個人と組織の満足度を高めるかにあります。
そのためには、以下のような視点が不可欠です。
「誰が何時間働いたか」よりも、「どのような成果を出し、組織にどう貢献したか」を見える化することが、納得感ある評価と柔軟な働き方を両立させます。
特に定性業務やチーム貢献が多い職場では、「数字だけの成果主義」は限界があります。上司との1on1や、チーム内でのフィードバックを重ねることが重要です。
時間や場所がバラバラでも、何を成果とするかが曖昧だと、メンバー間の誤解や不満が生まれます。評価基準の透明化や、マネージャーによる説明責任が求められます。
改革の中で忘れてはならないのが、働く人の“納得感”と“やりがい”です。
たとえば:
このような視点が揃ってこそ、本当の意味での“成果主義”が機能し、社員が自律的に働ける組織文化が生まれます。
次回は、「“働きやすい”の落とし穴 — 優しいだけの職場が抱える問題とは?」というテーマで、「改革のやりすぎ」や「甘さ」が生む新たな課題について掘り下げていきます。
「働き方改革を進めたいけれど、管理職が動かない」
「制度を導入しても、現場での運用が止まってしまう」
そんな課題を抱えている企業は少なくありません。
その多くに共通するのが、“中間管理職がボトルネック”になっている構図です。
今回は、なぜ管理職が働き方改革を阻んでしまうのか?そして、どうすればその“無意識の抵抗”を超えていけるのか?を考えていきます。
改革を“止めている”ように見える管理職も、実は個人として反対しているわけではないケースがほとんどです。背景には、次のような複雑な事情があります。
→ テレワークやフレックスを部下に認めて失敗したら、責任を問われるのは管理職自身。新しい制度を使わせるより、従来通りのやり方の方が“安全”なのです。
→ 働き方改革を進める一方で、評価軸が「稼働時間」や「上司の目に見える努力」に偏っていると、部下の柔軟な働き方を推奨しにくくなります。
→ 経営層から「改革を進めろ」と言われても、それが自分の人事評価に関係ないなら、どうして優先的に取り組む必要があるでしょうか。
中間管理職が変わらないと、現場も変わりません。
そのためにまず必要なのが、彼らに“改革の当事者”としての意識を持ってもらうことです。
「生産性向上」や「多様な働き方推進」といった抽象的な方針だけでは、現場管理職は動けません。
「業務の属人化を防ぐこと」「部下のモチベーションを高めることで成果につなげること」など、“自分のマネジメント課題とどうつながるのか”を言語化することが重要です。
心理的安全性がないと、行動は変わりません。小さな実験的取り組みを認め、成果だけでなく「挑戦した姿勢」も評価する文化を示しましょう。
働き方改革が「単なる負担増」になってしまわないよう、業務の見直しやDX支援、属人化解消の取り組みなどとセットで進めることが理想です。
改革が管理職任せになってしまうと、組織の中で「やる人とやらない人」の差が生まれ、かえって不公平感が増します。
人事・総務に限らず、現場の管理職や経営層も巻き込んだ横断チームを作ることで、「経営と現場の橋渡し」ができます。
研修や意見交換の場を設け、他部門の事例や悩みを共有することで、孤立感や抵抗感を和らげることができます。
次回は、「『時短』だけが改革ではない—成果主義と納得感のバランスをどうとるか」と題し、時間削減偏重の改革に潜む落とし穴と、成果を出せる働き方改革のあり方を掘り下げます。
テレワーク制度を導入したにもかかわらず、
「結局、みんな出社している」
「制度はあるのに、誰も使っていない」
と感じたことはありませんか?
これは「出社圧力」という無言の空気が職場に漂っている可能性があります。今回は、この目に見えにくい“空気”の正体と、それを解消するための具体策について考えていきましょう。
制度としてはテレワークが可能であっても、実際に利用されない理由は以下のような心理的・文化的な要因によるものが多いです。
上司が出社を前提にしている場合、部下は「在宅では評価されにくい」「顔を出さないと心証が悪い」と感じます。
テレワークは一人では使いにくい制度です。「自分だけが在宅だとサボっていると思われそう」「連絡しづらい」と感じてしまい、結果的に全員出社…という悪循環に。
紙の書類への押印、対面での承認、固定電話対応など、制度だけでは解決できない“仕組みの壁”が残っているケースもあります。
現場に与える影響が大きいのは管理職です。まずはマネージャー層が率先して在宅勤務を活用することで、テレワークが「使ってよいもの」として自然に根付きます。
「週1回以上の在宅勤務を目標」といった目安を設定し、部署ごとの実施状況を社内で共有することで、心理的ハードルが下がります。表彰や称賛の仕組みを加えるのも効果的です。
書類の電子化やクラウド活用、チャットでの承認プロセスなど、「物理的に出社しなくても仕事が進む仕組み」を整えることが根本解決につながります。
テレワークは、万能な働き方ではありません。業種や職種によっては難しいケースもあります。ただ重要なのは、「選択肢がある」「働く人が選べる」という状態を整えることです。
出社も在宅もフラットに選べる環境こそが、社員の納得感と生産性を生み出します。そしてそれは、離職防止や採用強化といった経営面にもつながっていきます。
次回は、「管理職がボトルネック?ミドルマネジメントと働き方改革のジレンマ」と題して、改革を阻む“中間管理職の本音”に焦点を当てていきます。